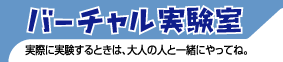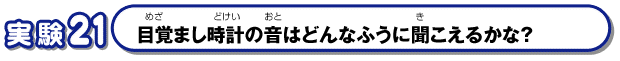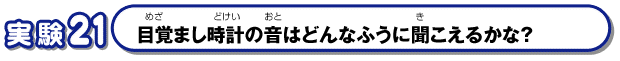|
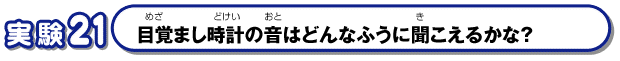
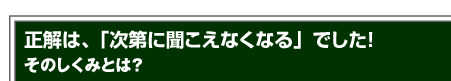 |
 |
 |
音は、物質から発生する振動が、他の物質を介して波のように連続して伝わっていきます。
音を伝える物質のこと「媒質(ばいしつ)」と言います。媒質には、空気などの「気体」、水などの「液体」、金属などの「固体」があります。
目覚まし時計の音が、空気中を伝わる場合を考えてみましょう。
| (1) |
目覚まし時計が鳴らないときは、まわりの空気は何も変化が起こっていません。 |
| (2) |
目覚まし時計が鳴ると、目覚まし時計の出す振動が直近の空気(媒質)を押し出したり引き戻したりして、空気の濃い部分(密)と薄い部分(疎)を作りだします。こうしてできた濃い部分と薄い部分がまわりの空気に伝わっていきます。
これを「疎密波(そみつは)」または「縦波(たてなみ)」と言います。 |
| (3) |
この振動が私たちの耳の奥の鼓膜(こまく)を振動させて、その信号が脳に伝わり、音として認識します。 |
媒質が固体や液体の場合にも、音源から出る振動が直近の媒質を押し出したり引き戻したりして、同じように疎密波が生じ、音が伝わっていきます。一般的に、液体よりも固体の方が音を早く大きく伝えます。
さて、今回の実験について考えてみましょう。
容器の中の空気圧を小さくしていくと、徐々に空気がなくなっていきます。
すると、音を伝えるための媒質が少なくなる(媒質の密度が小さくなる)ので、振動が伝わりにくくなり、結果として音が聞こえにくくなります。
そして、容器の中が真空(空気がゼロ)になると、音はまったく聞こえなくなります。
■電波ってなに?
携帯電話や通信衛星などが受発信する電波は、音波とは性質が異なります。例えば、次のような特徴があります。
| (1) |
音波は媒質が無いと伝わりませんが、電波は媒質が無くても伝わります。 |
| (2) |
音波が秒速330mで伝わるのに比べ、電波は秒速約300,000,000m(1秒間に地球を約7.5周する速さ)で伝わります。 |
| (3) |
音波は振動の方向が波の進行方向と同じ(縦波)ですが、電波は振動の方向が波の進行方向に対し垂直(横波)です。 |
|
|
 |
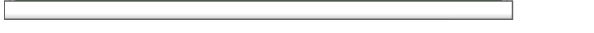 |
|

 |