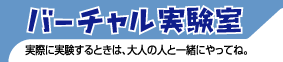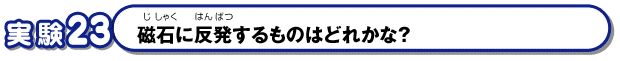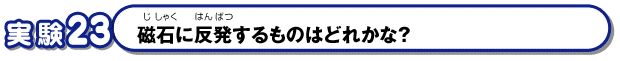磁石にくっついたり反発したりするのは、その物質を構成している「原子」に含まれる「電子」の動きが関係しています。電子は、原子核のまわりで運動していますが、電子自身も回転運動しており、この回転運動が磁石に付いたり反発したりする性質を原子に与えています。
電子自身の回転運動のことを『スピン』と言い、右回り(時計回り)と左回り(反時計回り)があります。
原子は、外部にある磁石の力の及ぶ範囲内(『磁界』とか『磁場』と言います)にあると、磁場の影響を受けて電子スピンの方向が変化して、磁石に付いたり反発したりするようになります。このような性質のことを『磁性』と言います。
シャープペンシルの芯は黒鉛(炭素:C)でできています。炭素は、磁場の中では磁石の力に抵抗する向きにスピンを揃えようとします。そのため、磁石のN極/S極どちらを近づけても、反発します。このような磁性を示す物質のことを『反磁性体』と言います。
反磁性体には、炭素のほかに、金(Au)、銀(Ag)、銅(Cu)などの金属や水(H2O)、エタノール(C2H5OH)などがあります。
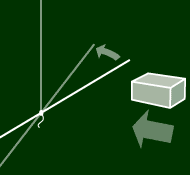 |
シャープペンシルの先端に磁石を近づけると、接触するギリギリ直前あたりで、くるっと逃げるように回ります。 |
ビデオテープは、磁石に引き付けられます。ビデオテープは、磁性粉がベースフィルムの上に接着剤でくっつけられたものです。磁性粉には鉄(Fe)やγ-Fe2O3が使われています。
Feは、磁石のN極/S極どちらを近づけても、くっつく方向にスピンを揃えようとする性質があり、『強磁性体』と呼ばれています。強磁性体には、ビデオテープのほかに、ニッケル(Ni)やコバルト(Co)などがあります。
一方、γ-Fe2O3は、右回りのスピン、左回りのスピンの両方を持っていますが、大きさと数が異なるために磁石に付く性質を持つもので、特に『フェリ磁性体』と言われています。
学校などの黒板に貼り付けて使われているマグネットは「フェライト磁石(BaO・6Fe2O3)」で、代表的なフェリ磁性体です。
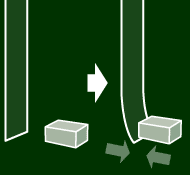 |
ビデオテープに磁石を近づけると、接触するギリギリ直前あたりで、吸い寄せられるようにくっつきます。 |
アルミニウム(Al)でできた一円玉は、磁石を近づけても、磁石にくっついたり、または反発するほどの大きな影響を受けません。
このような物質のことを『常磁性体』と言います。常磁性体にはアルミニウムのほかに、チタン(Ti)、マンガン(Mn)などがあります。
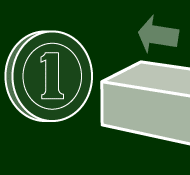 |
一円玉に磁石を近づけても、何の反応もありません。 |
さて、このページの冒頭で、水が『反磁性体』であることをご紹介しましたね。
水面にかなり強力な磁石(電磁石)を近づけると、水面が凹む現象を見ることができます。これは、旧約聖書第二話「出エジプト記」で預言者モーゼが海を二つに割って見せる現象になぞらえて、「モーゼ効果」と呼ばれています。
逆に、反磁性体の水に強磁性体(例えば塩化コバルト)を溶解した溶液の水面に、強力な磁石(電磁石)を近づけると、水面が盛り上ります。これは「逆モーゼ効果」と呼ばれています。
なかなかユーモアのある命名だとおもいませんか? |